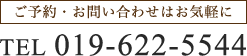糞便移植 part2
2024/03/21
2014年7月に、糞便移植について取り上げた。
糞便移植 | こけ玉のブログ (ameblo.jp)
初めて聞いたときはこのかなりインパクトのある治療法に驚かされた。
その後、この治療法は着実に進歩してきているらしい。
今回初めて耳にするという方のために簡単に紹介すると、この治療法は読んで字のごとく、他人の糞便を腸内に移植するという治療法である。
というか、もっと正確に言うと現在では糞便そのものを直接移植するのではなく、培養したり、調整する液体を混ぜたりしたものを移植するのであり、「他人の腸内細菌叢を移植する」という表現の方が正確かもしれない。
いずれ今や腸内環境を整えることがあらゆる疾患において重要な役割を果たしていることは周知のことであるが、食を変えただけではなかなか整えきれないもの。
そこで健康な人の糞便を移植して有用な腸内細菌叢を再獲得しようというものである。
実はこのような治療法は1958年や1981年に既に報告されていたらしい。
しかし、他人の糞便を移植するというのが感覚的に受け入れがたかったのか、他の疾患の感染を恐れたのか、はたまた薬剤至上主義のためか、理由は定かではないが医学界ではあまり顧みられることなく現在に至ったようである。
この治療法の臨床試験が初めて行われたのは2009年というから注目されてからまだ20年もたっていない。
前回取り上げた時は以下の疾患への有用性が期待されていた。
抗生物質に耐性を持つクロストリジウム菌感染症の他に、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群などの胃腸疾患、糖尿病などの代謝性疾患、パーキンソン病などの神経疾患、そして胃がんや、喘息、アトピー、慢性疲労症候群、線維筋痛症、等々多くの疾患があげられていた。
肥満・メタボに対しては痩せている人の糞便注入も研究されているとのことであった。
感染予防のためにも糞便のドナーは当然ながら健康な人の糞便が選ばれるが、当時から糞便そのものではなく、腸内細菌を人工的に培養したものに置き換えられないかという研究はすでに始まっていた。
糞便移植はどこまで臨床の場を広げているのだろうか。
この間の報告の中には潰瘍性大腸炎や自閉症スペクトラム障害、双極性障害、アルコール依存症、コロナ感染症(回復力アップ)などに効果があったという報告もある。
そしてそれはどうやら、がんにも効果があるかもしれないという。
『Science』(2月5日付)に掲載された最新の研究では、ほとんどの治療で効果が見られなかった皮膚がんの患者に糞便移植を行ったところ、腫瘍が小さくなったという。
進行した黒色腫(皮膚がんの一種)には、ベンブロリズマブという「免疫チェックポイント阻害剤」がよく使われるそうだ。
だが50~70%の患者は結局、治療の甲斐なく病状が悪化してしまう。
そして、もしこの免疫療法が効かなければ、現在それ以上の治療法はなく、完全にお手上げとなるという。
そこでピッツバーグ大学をはじめとするグループは、ペンブロリズマブの効果をアップさせる腸内細菌がないか調べてみることにした。
この治療がよく効いた患者の大便から腸内細菌を集めて、それをあまり効かなかった患者に移植するのだ。
免疫療法の効果を左右する細菌をピンポイントで見つけ出すことは難しいため、大便に含まれていた腸内細菌を丸ごと移植する。
それから12週間後、患者15名中6名は、腫瘍が小さくなっていたか、少なくとも大きくはなっていないことが分かったという。
中には疲労のような副作用が出た患者もいたが、それも許容範囲だったとのことだ。
またその6名の腸内細菌は、最初に腸内細菌が調べられたときよりも、数が増えていたそうだ。
さらに血液と腫瘍を分析したところ、「骨髄細胞」という免疫を弱らせる細胞や薬の効きにくさに関係する免疫系分子が減っており、その一方で免疫の獲得に大切な役割を果たしている「免疫記憶細胞」が増えていることも分かった。
こうした結果は、一部の腸内細菌が薬への反応を高め、免疫系が腫瘍をうまく殺せるよう手助けしてくれることを示しているそうだ。
このように着実に糞便移植法は臨床の場を広げているようだ。
だが、同時に、臨床例が増えて来るに従って、糞便移植法の危険性も明らかになってきている。
偽膜性腸炎という疾患の治療を行った研究論文では、「移植する便を提供した人(ドナー)に肥満傾向があったところ、移植後に移植を受けた人(レシピエント)が、偽膜性腸炎は治ったものの、太り始めた」という。
同じ食事を摂っていても太りやすい人と太りにくい人に分かれるのは、腸内細菌叢の差が大きな要因となっているそうなのだが、その太りやすいという「体質」が、糞便微生物移植で移ってしまったというのは、衝撃的な事実として受け止められている。
他にも、「移植をしてもあまり症状が改善しかなった」「発熱、痛み、むくみなどの副作用が認められた」などの報告があがっていて、糞便移植は、決して、100%安全で、100%効果のある治療法ではないという認識も広がり始めている。
糞便移植で多少太った程度であれば、まだ大きな問題はないが、死亡例も出るとなっては問題の次元が変わってくる。
2019年6月、糞便移植をした後に感染症で死亡した例がアメリカで報告された。
米食品医薬品局(FDA)によると、臨床試験で糞便移植を受けた患者のうち2人が、多剤耐性菌に感染し、このうちの1人が死亡し、FDAは糞便移植に対して警告を出したという。
当然、この例がすべてに当てはまるわけではないが、より慎重さが求められるようになるだろうとも言われている。
糞便移植は、これまで投薬や手術でしか治療できなかった病気の治療を、変える可能性がある医療技術ではあるが、一方で、予測できない「副作用」が起こるリスクは、まだまだ大きい。
未知の感染症にかかる可能性、そして最悪死亡する可能性も否定できない。
さらに、便を提供する側にとっては病原性のない腸内細菌であっても、提供を受ける側には病原性を発現する可能性もある。
そのようなケースでは、単に既知の感染症のチェックだけでは防御しきれず、どのような腸内細菌が、どのような人にどのような影響を与えるのかについては、まだまだ未知の部分が多いのだと、小西統合医療内科の小西医師は語っている。
一種のブームに乗っているかのように、糞便移植を行う症例数が増えてきていることに対し、今後、厳格な臨床研究を積み重ね、慎重に適応症例を決めていかなければ、その技術の可能性までもが失われてしまいうと警鐘が鳴らされている。
極めて有用な技術だからこそ、大切に育てていかなければならないということのようである。
体のこと、あれこれ
- 2025/12/09
- ブルセラ症
- 2025/07/22
- 失われた視覚を取り戻す最先端技術
- 2025/06/23
- 造語依存型失語症
- 2025/05/22
- フレゴリ症候群
- 2025/03/26
- 化学物質を検出するデバイス
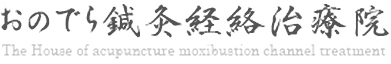
| 所在地 | 〒020-0132 岩手県盛岡市西青山3丁目40-70 |
|---|---|
| 営業時間 | 平日/9:00~19:00 土曜・祝日/9:00~17:00 |
| 休日 | 日曜日 |
| TEL | 019-622-5544 |