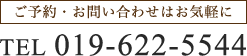アルコールと脳
2025/02/13
幸か不幸か、自分はアルコールに弱い。
たいがいビール350ml1本で十分満足できる。
おそらく体質的に分解酵素が少ないのだろう。
だが人によっては自らを破滅に導くまでやめられない人もいる。
一体、依存症とはどうなっているのだろう。
アルコールと脳の関係に関しては様々な研究がなされている。
依存症に導かれる仕組みも生理学的に解明されてきている。
現在は依存症を絶つ薬も開発されてきている。
断酒会などで苦しみながら依存症から脱出するのではなく、服薬で楽にやめられる日が訪れようとしている。
きっと、酒で失敗する人も次第に少なくなっていくことだろう。
ちなみに、酒にまつわるあの常識も覆される研究も進んでいる。
これは酒好きの人にはちょっと残念かも(笑)。
そもそも、アルコールを飲むと体はどのように反応するのだろうか。
アルコールは飲むと小腸で吸収され、血流にのる。
身体はアルコールを毒物と見なし、肝臓で分解してなるべく早く排出しようとする。
アルコールはまずアセトアルデヒドという毒性のある化学物質になる。
これが二日酔いの原因で、更に別の酵素によって無害のアセテートに変わり、尿となって排出される。
しかし、分解しきれなかったアルコールに含まれるエタノールは血液を循環し、最終的に脳へと到達する。
脳には病原菌など害のあるものを脳内へ入れないフィルターがあるが、エタノールは脂肪との親和性が高いので、脳内に入り込み、ニューロン間の信号伝達をめちゃくちゃにしてしまい、運動バランスや正常な会話を阻害して、いわゆる典型的な酔っぱらいの症状を示すことになる。
脳はアクセルとブレーキを使い分けることで様々な生命活動を維持させるが、アルコールは機能を抑制、すなわちブレーキの作用を持つので、運動を調整する小脳が抑制されると千鳥足になる。
自制や社会的抑制をつかさどる所が抑制されると気が大きくなり、感情的になり、危険な決断をしやすくなる。
ちなみに、酔った状態で通販サイトを見るとついつい余計なものまで買いがちになるのはこの所為なのでご注意を(笑)。
そして、短時間に大量のアルコールを摂取すると分解処理が追い付かず、脊髄が働かなくなり、最悪、心拍や呼吸の停止を引き起こしてしまう。
だから一気飲みはやってはいけないのだ。
アルコールが及ぼす害は脳や脊髄だけにとどまらない。
長期的な飲酒によって炎症を引き起こし(湿疹がひどくなるとか)、ホルモン量へ干渉し、細胞のDNA構造の修復を阻害したりもする。
ある種の癌を助長させることも明らかになっている。
そこまでの毒性を持ちながら、人はなぜアルコール依存症になってしまうのだろう。
酒のまつわる記憶というのは非常に強い。
それは何かの経験が脳に保存される通常の記憶とは違い、飲酒したときに活動した特定の神経線維の集団が形成されるという「記憶痕跡」というもののせいらしい。
これは物理的な存在のために、記憶が薄れるということがなく、どれだけ断酒を続けてもアルコールと関連づいたサイン(ラベルや赤ちょうちんなど)がトリガーとなって飲酒への渇望が引き起こされる。
これは回路が出来上がっているために、単純に意志の力でどうにかできるものではない。
マウス実験ではアルコールで活性化された神経線維の集団に対し、クロザニンN-オキシドという薬剤で鎮静化させてみたら、依存傾向に改善が見られたという。
マウスではこのアルコール関連の記憶痕跡が作られるまで15日間しかかからなかったという。
人間の場合はこの記憶痕跡がどのくらいの日数で作られるかはまだ分かっていないが、選択的にこの神経線維集団を抑制できれば依存症の改善ができるかもしれない。
また、依存症に関しては細胞レベルで記憶形成が行われているとの実験結果も出ている。
上述でアルコールが体内に入った際の過程を説明したが、肝臓で分解される際に「酢酸塩」という物質も生まれている。
この酢酸塩は血液の中を流れ、肝臓から脳の記憶を司る領域である海馬の細胞まで到達する。
すると今度は「ACSS2」という酵素が反応する。
このACSS2と酢酸塩との反応によって、遺伝子そのものは変えないけれども、遺伝子の機能を変えるという。
これが最終的にアルコールにまつわる強力な記憶を作るのだそうだ。
この他にも「ノッチシナリング」というたんぱく質が関与する記憶パターンも明らかになっている。
こうしてみると、アルコールの記憶形成は二重にも三重にも行われており、非常に強力であることが分かる。
これでは意志の力ではあらがえないかもしれない。
ちなみに、マウス実験ではACSS2のレベルを下げるとアルコールに対する嗜好性を示さなかったという。
アルコールにまつわる神経線維の集団に対する働きかけやACSS2を抑える方法はまだ確立はされていないようなだが、それら複合的な治療法が確立されれば、アルコール依存症患者は劇的に減らすことができるかもしれない。
現時点で行われている治療法を一つ紹介したい。
イギリスでは「シンクレアメソッド」といって、際限もなく飲みたくなる欲求を抑えることのできる服薬も含めた治療法が開発されている。
これは麻薬拮抗薬のナルトレキソンを飲酒の1時間前に服用すると、脳内のアルコールエンドルフィンをブロックし、中毒性を減らすことができるというもの。
完全に酒を断ちたくない依存症患者にはうってつけなのだそうだ。
なんとも至れり尽くせりになったものだ。
やれやれ、と思われるかもしれない。
しかし、完全に断とうとして失敗し、挫折するよりもほどほどに飲みながら徐々に改善させていく方が80%の確率で成功するという。
もちろん、服薬だけではなく、酒をやめることへの決意と、それに伴う自制心も求められはするが、これまでのアルコールを悪魔と見なし、意志の力で絶つ方法はある意味懲罰的であり、断酒会への参加に対し恐怖を抱かせるもとにもなっていた。
しかし、この方法ならばそのようなことはないらしい。
非常に意味のある治療法のようだ。
詳しい治療法は下記をご参照いただきたい。
アルコール依存症の救世主なるか?飲む前に飲む薬で依存症を取り除いていく「シンクレアメソッド」法(英研究) : カラパイア (karapaia.com)
ところで、「酒は百薬の長」と言われる。
飲みすぎれば数々の失敗を引き起こす酒も、適量さえ守ればかえって健康にいいのだと。
ところが、そんな酒飲みにとって都合のいい言葉が根底から覆される研究結果が露わになった。
「酒の適量はない」というのである。
体質や個人差はもちろんあるだろうが、飲酒は必ずその代償を支払うことになると。
これまでに「グラスワイン女性なら1杯、男性なら一日2杯程度なら心臓及び循環器系に良いようだ」という研究結果もあったが、ワシントン大学のマックス博士らは、それはアルコールの持つ些細な一面でしかなく、総合的にみるとガン・怪我・精神疾患・脳の早老化などに関連しており、飲酒量との関連を調べても「適量」というものは存在しないという。
もちろん個人差はあるので、酒やたばこを飲んでいても長生きする人もいる。
しかし、上述のようにアルコールは人体にとって毒でしかないので、そのような特異な例を持ち出して普通の人が飲酒し続けることはリスクを増大させるだけだろう。
別の研究ではアルコールを分解するために酷使した肝臓は、どれほど酒が強い人でも100%完全に元に戻ることはないそうだ。
私たちは強い人も、弱い人も、皆身を削って酒を飲み続けていることを自覚した方がいいのかもしれない。
さて、今夜は何を飲みますか(笑)?
体のこと、あれこれ
- 2026/01/07
- オーバードーズ
- 2025/12/27
- 「処方カスケード」と「ポリファーマシー」
- 2025/12/09
- ブルセラ症
- 2025/07/22
- 失われた視覚を取り戻す最先端技術
- 2025/06/23
- 造語依存型失語症
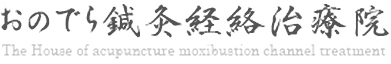
| 所在地 | 〒020-0132 岩手県盛岡市西青山3丁目40-70 |
|---|---|
| 営業時間 | 平日/9:00~19:00 土曜・祝日/9:00~17:00 |
| 休日 | 日曜日 |
| TEL | 019-622-5544 |