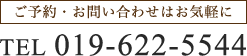「病院で死ぬということ」~山崎章郎
2018/03/20
あなたは死をどこで迎えたいだろうか?
それともそんなことはまだ露ほども考えられないだろうか?
昨年、日本男子の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳となった。
自分の場合だと平均寿命を生きるとすればあと24~25年といったところである。
しかし、こんなことを書いている明日にでも、何らかの事故で死ぬかもしれない。
そろそろ山シーズンが始まるが、山で不運にもクマと遭遇し死んでしまうかもしれない。
何らかの疾患を患い、それが急性疾患であれば1か月後には死んでいる可能性もある。
人の人生などは不確定なのだ。
不確定だからこそ「一日一日を大切に」などと言われても実感がわかず、自分などは無為に時間を過ごしてしまうのである。
しかし、期限がもし目の前に提示されたとしたら、こんな自分でもきっと生き方が変わるだろうと思う。
この本は1990年に出版されたもので、もうかれこれ30年近く前に書かれたものである。当時の癌患者が置かれた医療状況の中で、一人の人間として尊厳を持った死を迎えるために医療とはどうあるべきかを模索した著書である。
当時に比べれば癌治療も進歩し、死亡率自体は減少してきている。様々な角度から新しい治療方法も研究され、決して死を意味する疾患ではなくなりつつある。
しかし、高齢化に伴い、その実数は年を追うごとに増え続けている。
当然ながらすべての人に死は訪れるものだし、死に至らしめる疾患は癌以外にも多数あるけれども、三大疾病と言われる癌、脳卒中、心疾患の中で見ると、
脳卒中や心疾患は発症が急激であり、そしてまた死を迎える場合も急激である。
遺族にとっては心の準備が整っていないうちに大切な人を亡くしてしまうという悲しみが襲ってくるのだ。
一方で癌の場合は発症から死を迎えるまでの期間が比較的長く、さらに明確な意識を保ったまま推移する。
つまり、本人や家族が現実的な死を見つめながらともに生きるという他の二大疾患とはまた違う特殊な面もあるのである。
そんな患者のために、あなただったら日本の医療はどうあってほしいだろうか。
山崎先生の人生観が変わったのは1983年の南極に向かう海の上でのことだった。
南極海の地質調査船の船医として乗り込んでいた山崎先生は、日本から多くの本を持ち込んでいた。
その中の一冊にエリザベス・キュプラー・ロス著「死ぬ瞬間」があった。
医師という「死」に携わる職業に就くものとして、何らかの参考になればという軽い気持ちで手にした本だった。
しかし、そこに書かれていた内容は、それまで「あたり前」と思っていた終末期患者への対応の価値観を大きく変えるものだったのである。
それまでの終末期にある患者さんにとっての死とはどんなものだったのだろう。
本著の前半部分では山崎先生がそれまで見聞きしてきた典型的な事例がいくつか紹介されている。
そのお一人お一人にとっての死は、彼あるいは彼女自身のものではなく、家族や医療側のものだったのである。
もちろんすべての人にとって告知が正しい選択になるとは限らない。
しかし、「死の告知は患者に絶望を与え、生きる気力を奪ってしまう」という理由から、告知をされなかった彼らの多くはどのような最期を迎えただろうか。
最初は医者を信じ、家族を信じ、自分は完治すると信じ疑わない。
しかし、病状は悪化の一途をたどる。
疑問を呈しても周りは「大丈夫、頑張って、治るから」と答えるばかり。
いつしか変わっていく身体に不安は増し、周囲の者たちに対する不信感は募り、徐々に迫り来る死の予感とともに、裏切られたとの思いの中で絶望をしていくことが多いという。
また、ある医師はそれまで癌と闘うことに一生懸命だったが、余命いくばくもないところまで来ると、まるで興味を失ったかのようにほとんど患者のもとを訪れることもなくなり、
いざ最期という段になり、「最後まであきらめない。尊い命を長らえさせる」という「美しい信念?」のもと、本人の苦しみなど無視するがごとく、あらゆる延命治療を施し、わずかばかり最期を先延ばしさせる。
繰り返すが、人の価値観は様々である。
信念や性格も様々。
すべての患者に告知が正しいものとは限らない。
また、家族の中にも、たとえそれが数分の先延ばしであっても「最後まであきらめない」ことに生きることの意味を見出す人もいる。
だからこそ上記のような医療が受け入れられ、山崎先生にしてもやるせなさを感じながらもそれが「あたり前の医療」として信じられてきたのである。
そんな山崎先生を変えたのがエリザベス・キュプラー・ロス著の「死ぬ瞬間」の以下の一節だった。
「患者がその生の終わりを住み慣れた、愛する環境で過ごすことを許されるのならば患者のために環境を調整することはほとんどいらない。家族は彼をよく知っているから鎮痛剤の代わりに彼の好きな一杯のブドウ酒をついでやるだろう。家で作ったスープの香りは彼の食欲を刺激し、二さじか三さじ液体が喉を通るかもしれない。それは輸血よりも彼にとってははるかにうれしいことではないだろうか」
ここにはなんと尊厳に満ちた最期が描かれていることだろうか。
当然ながら終末期に鎮痛剤はいらないというのではなく、痛みと言っても心因性の痛みの場合には鎮痛剤より、よっぽど一杯のブドウ酒の方が効くだろうという意味である。
一人の人間が最期を迎えるにあたって、望むままにかなえさせようとする尊重の念があふれている。
著書の後半は山崎先生が意識を変えてから向き合ってきた人々の事例が紹介されている。
しかし、意識を変えたからと言って最初からすべての人にうまく対応できたわけではない。
そこにはまだまだ足りない何かや、課題が正直に語られている。
一人一人がまるでドラマでも見るかのようなエピソードにあふれている。
先生ご自身の身近な人も逝ってしまう。
最後の間際まで意識を保ち、別れの挨拶を周囲の人とかわしながら、やがて眠るように逝ってしまう。
心から「ああ自分もこんな最期が迎えられたら、生きてきた意味も肯定できるかもしれない」とそんな風に感じさせられるのである。
ところで、現在日本におけるホスピスはどのような現状なのだろうか。
2017年の時点で(日本ホスピス緩和ケア協会調べ)、全国では394施設、8068床のホスピスがあるとされている。
ホスピスの利用は1990年に厚労省がスタートさせた「緩和ケア病床承認制度」との兼ね合いで悪性腫瘍とエイズの疾患で、病状が末期であることが条件とされている。
では2017年にガンで亡くなられた方はどのくらいかというと、およそ378000名とのこと。
あまりにも実情に合わなすぎる。
経済大国ではなくても、北欧のように充実した医療・社会保障制度を作り上げている国もあれば、世界三位の経済大国ながら軍事費を聖域とし、医療・社会保障制度を後退させていく国もある。
結局、あたりまえの話だが、何を優先させるか次第で国のありようは変わるということだ。
ちなみに、我が岩手の現状はというと、日本ホスピス緩和ケア協会のサイトによると県内の病院でホスピス科を併設しているのは5件だけだった。
ターミナルケア可能な老人ホームは随分と増えてきてはいるようだけれども、まだまだ岩手における終末期医療やホスピスは十分とは言えないようである。
また、自宅での最期を迎えたいと希望する人は8割にも上る。
確かに戦後間もない昭和26(1951)年には82.5%の方が自宅で亡くなられていたそうだ。
しかし、現在では逆に8割以上の方が病院で亡くなられていて、自宅で最期を迎える方は13.0%にまで減っている。
ただし独居老人は逆に孤独死を恐れ、病院や施設での最期を望む。
その人の生きてきた道が最期にも表れるのかもしれない。
現在、「告知を受けた上での尊厳死」は広く認知され、終末期の延命治療は望まない人は多数派となっている。
自分の母親も時々そのことを口にしているし、自分自身もいざとなったら延命治療は望まないし、ビビリなのでもし薬剤がきかず痛みが続くようなら安楽死さえさせて欲しいと思う。
もちろん、最後の最後まで闘い切る生き方というのも非常に気高く、とても勇気のある生き方だと思う。
また、告知など受けずに、仮に命の期限が近いとしても特別なことは何もせず、求められる治療を淡々と受け止め、飄々と生きる生き方というのもありだ。
どれが正しく、どれが正しくないというものではない。
そして、住み慣れた我が家で、家族や使い慣れた道具に囲まれながら逝くか。
病院で、医学的な措置の安心さに囲まれながら逝くか。
さて、あなたはどこで、どんな最期を迎えたいだろうか?